69会は1969年に入学し、体育クラブに所属した同級生の集まりです。学生時代から親交は深く、卒業後もゴルフや飲み会で繋がりを保持してきました。2011年に、校友会に団体登録を行い、会の活動報告、催しの案内を校友会ホームページ(校友団体情報)に投稿しています。
2011年11月、校友センターのご支援・助言を戴き、還暦祝賀会を盛大に開催し、49名が出席しました。(4月開催の予定でしたが東日本大震災により延期)その際、次回は古希の祝賀会を開催しようとの合意があり、今回の開催に至った次第です。
今年、2019年は多くの仲間が古希を迎える(数えで)とともに、入学50周年であり、記念すべき年であるという事で、以下の通り開催しました。
開催日時 4月14日(日曜日) 12:30~15:00
会場 白金キャンパス本館10階 大会議室
出席者 53名
来賓 学生部長 亀ヶ谷純一教授(学長補佐)
同窓会 竹越浩一会長 (校友会副会長)
出席者の出身クラブ
アーチェリー、アメリカンフットボール、応援団、空手道、硬式テニス、山岳、サッカー、自動車、射撃、柔道、少林寺拳法、水上スキーモーターボート、軟式テニス、日本拳法、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、野球、ヨット、ラグビー、陸上競技、ワンダーフォーゲル。
会の流れ、様子
冒頭、物故者への追悼を行い、次に主催者代表の大谷明君 体育会執行部 第20代委員長 が挨拶を行いました。
続いて、亀ヶ谷教授から母校の様子、体育会クラブの活動状況、今後の取り組みについてお話があり、又、竹越会長からは今後とも、同窓会の盛り上がりに寄与してもらいたいとのお話があり、皆、真面目に(乾杯の前の祝辞でしたから)聞いていました。
乾杯の音頭、発声は数多くの遠隔地からの出席者の中で一番遠くから出席した高橋修史君(旭川市、山岳部OB)が行いました。関東地方以外から出席者の道府県は以下です。北海道2人、山形県、石川県、静岡県2人、愛知県、大阪府、広島県2人、福岡県、大分県。
乾杯の後、ちょうど良い機会という事で、野球部OB会前事務局長(竹内公一君)から謝辞がありました。(2013年、明治学院150周年、野球部記念試合終了後のパーティーの際、多くの体育会クラブOB会が野球部に寄付を行いましたが、そのお礼です。)
歓談の合間には、各クラブ順に出席者が近況を報告し、引き続き、紫色の「ちゃんちゃんこ」を着て、1人ずつ写真撮影しました。
出席者の中にはおよそ50年振りに会う仲間の姿や変貌発展を遂げた白金キャンパスに驚いたり、今昔の思いの中、旧交と親睦を深めました。
会の中盤には、プロジェクターで、動画及び写真の映写を行いました。
動画は2013年11月24日「明治学院150周年記念、野球部記念試合:神宮球場での対東京大学戦」、です。沢山の同窓生、教職員、学生が盛り上がった事に改めて感激しました。
写真は白金通信(1969年~1973年の在籍期間中の)抜粋「全共闘学生運動、野球部首都リーグ優勝、三浦土地購入問題など」我々にとって忘れられない思い出です。
※(白金通信は図書館に保存されています。校友会A会員になれば図書館に入館、閲覧ができます。白金通信は持ち出し禁止の蔵書のひとつですので、記事の写真撮影が許されました)
終盤には、応援団チアリーディング部の演技があり、出席者全員から感嘆の声が上りました。
最後は、全員で、声高らかに、応援歌、校歌を合唱しました。
閉会にあたりましては、世話人代表が、「配布した明治学院大学学校案内本を持ち帰って、母校を再認識し、孫、親族に明治学院大学を奨励して欲しい」と締め括りました。
尚、開会前、11:30からは体育会執行部4年生の案内によるキャンパスツアーを行い、約20名が参加し、卒業後、初めて、久しぶりに訪れた同窓生は、明治学院の歴史、文化財の素晴らしさに感銘し、現在の施設、学生の環境に羨慕の想いが積もった様です。
今回の催しにご協力、資料を提供して戴きました、校友センター、学生部、広報室、図書館、入試センター及び学院長室の方々に厚く御礼申し上げます。
投稿者 徳沢幸人 応援団OB

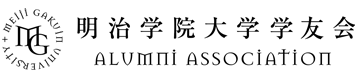
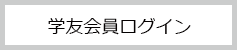
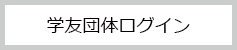

![img016+(4)[3]](https://gakuyukai.meijigakuin.ac.jp/images/2020/02/img016-43.jpg)
![img016+(8)[4]](https://gakuyukai.meijigakuin.ac.jp/images/2020/02/img016-84.jpg)
![img015+(10)[1]](https://gakuyukai.meijigakuin.ac.jp/images/2019/11/img015-101.jpg)







