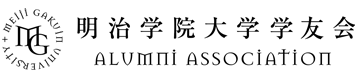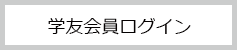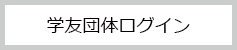当ゼミは、本学元客員教授の中島耕二先生のご指導のもと、設立して7年が経過しようとしています。その間、J.C.ヘボン博士、S.R.ブラウン博士、G.F.フルベッキ博士、W.インブリー博士、H.ルーミス博士、横浜の女性宣教師たち、J.H.バラ博士の各書簡集あるいは伝記類の輪読、フィールド・ワークの適時な実施、並びにキリスト教史学会大会や外国人居留地研究会全国大会など各研究会に参加しながら活動をしてきました。 4月からは、築地大学校(明治学院の前身)教授・舎監、明治学院神学部教授であったトーマス・T・アレキサンダー博士の曾孫のジョアンナ・シェルトン著『わたしの家族の明治日本』(文藝春秋、2018年10月)を輪読する予定をしています。
今回はゼミの一環として、中島先生が講演された「NPO法人築地居留地研究会 平成31年3月度定例報告会」に、ゼミ生9名が参加したので報告させていただきます。
開催日時や会場並びに次第など概要は下記のとおりでありました。
主催:NPO法人築地居留地研究会
後援:東京都中央区
日時:2019(平成31)年3月23日(土)14:00 ~ 17:45
会場:聖路加国際大学 聖路加臨床学術センター 3階3302号室
東京都中央区築地3-6-2
次第:Ⅰ 開会にあたって 挨拶 NPO法人築地居留地研究会理事長 水野雅生
Ⅱ 定例報告会
テーマ:築地居留地と近代音楽 ―讃美歌と青年たちの出会い―
with 聖路加国際大学聖歌隊の皆さんによる合唱
講 師:中島耕二(なかじま こうじ)
東北大学博士(文学)、
築地居留地研究会理事、
明治学院大学元客員教授
Ⅲ 記念写真 聖路加国際病院旧館
Ⅳ エクスカーション 講演に関連した史跡案内
V 講師を囲んでのお茶会
Ⅵ 終了
参加者:約80名(満員)
中島先生が上記テーマで講演された内容については、ここでは配布された詳細なレジュメから抜粋し、項目を加えながらその骨子をご紹介いたします。
1.はじめに
日本の近代音楽、つまり洋楽の流入時期は、一般には1853年7月に黒船が浦賀に来航した時期と言われている。ペリー艦隊は軍楽隊を2組編成し、上陸、帰艦のたびに軍歌、アメリカ国歌やフォスターの曲などを演奏し、日本人に洋楽を聴かせていた。
一方、日米修好通商条約締結の翌年、1859年にはプロテスタント宣教師が来日、神奈川(横浜)ではヘボン夫妻、S.R.ブラウン一家が成仏寺に居住し、日曜日には礼拝を守り讃美歌を歌っていた。ブラウン一家はポータブル・オルガンを持参し、日本人の一般庶民に讃美歌の旋律を届けている。
2.築地居留地で育てられた近代音楽とそれを担った音楽青年たち
築地居留地では明治2(1869)年以降、カロザース宣教師夫妻の英語塾で少年、少女は讃美歌の指導を受けていた。後に音楽取調掛(後の東京音楽学校、現在の東京藝術大学音楽学部)の校長になる伊澤修二少年もここで学んだ。皆さんが聴いたり、歌ったりして良くご存じの童謡、文部省唱歌、歌曲、および県民歌など、日本を代表する曲を作った近代音楽家たちは、築地居留地と深い関係を持っている。以下、具体的に説明する。
➀ 西村庄太郎(1864~1931)
明治13(1880)年、横浜のバラ学校(ヘボン塾の後身)が築地居留地7番に新校舎を建てて移転し、築地大学校となる。そのとき生徒の一人であった西村少年も一緒に築地にやってきた。同少年は、横浜のヘボン塾でミス・マーシュ女性宣教師からオルガンの手ほどきを受け、短期間に「聖歌集」をマスターし、横浜第一長老教会(後の住吉町教会、現在の横浜指路教会)のオルガニストを頼まれるまでになった。彼が築地に来ると生徒仲間と新栄教会(戦時中、目黒に移転)に通い始めたが、早速オルガニストを依頼された。やがて彼のもとに音楽に関心を抱く後輩たちが集まって来て、新栄教会を教室にして彼から譜面の読み方やオルガンや洋楽の基礎を学ぶ。その音楽仲間に納所弁次郎、小山作之助、内田粂太郎の「築地大学校三羽烏」と呼ばれる音感に優れた生徒がいた。
西村は同校を卒業し札幌農学校(現在の北海道大学)に入学するが、父親が急死したために横浜に戻った。後に商用でアメリカに滞在中、高峰譲吉博士と出会いタカジアスターゼの日本での一手販売権を得て、日本で友人3人と製薬会社を立ち上げた。それが三人の友、つまり三共、現在の第一三共である。西村庄太郎は音楽家にならず実業家になったが、立派な近代音楽家たちを育てた先人となった。
➁ 納所弁次郎(1865~1936)
築地の戸川邸で生まれ、家でも幼い時から讃美歌を聴き、また新栄教会や露月町教会に姉たちに連れられて礼拝に出席していた。明治15(1882)年に17歳で築地大学校に入学し、正課として朝夕の礼拝で讃美歌を歌い、日曜日には新栄教会の礼拝に出席し讃美歌を歌い、讃美歌漬けの毎日だった。弁次郎は音楽に特別関心があったので、宣教師のトーマス・T・アレキサンダーや上級生の西村庄太郎から放課後、特別にオルガンの奏法の指導を受けていた。同校を卒業すると音楽取調掛に進学し、優秀な成績を残した。卒業後は母校の教員、学習院教授を長く務め、その間「言文一致唱歌」運動を広め、特に学校唱歌に力を注ぎ、文部省に採用されるようになった。
その代表作が「うさぎとかめ」や♪“桃から生まれた桃太郎” の「桃太郎」である。♪“もしもしかめよかめさんよ” の故郷は、この築地居留地と言って良いでしょう。
~上記二曲を聖路加国際大学聖歌隊の皆さんが美しいハーモニーで合唱された~
なお、文部大臣を歴任した永井道雄は、弁次郎の姪・永井次代(政治家永井柳太郎の妻)の子供にあたる。
➂ 小山作之助(1864~1927)
新潟県に生まれ16歳で上京し、明治13(1880)年に築地大学校に入学し、学校では弁次郎とずっと一緒に行動し、新栄教会の礼拝にも出席した。同校を出ると音楽取調掛に進学し、やはり優秀な成績を残し卒業後は、長く母校に務め教授となり、退官後も音楽教育に力を注 ぎ後進を指導した。中でも滝廉太郎を育て、ドイツ留学の世話をしたことは良く知られている。
代表作の♪“卯の花の匂う垣根に” という「夏は来ぬ」は小学校の音楽教科書にも採用された。ちなみに作詞はかの佐々木信綱である。
➃ 内田粂太郎(1861~1941)
明治12(1879)年、17歳のとき群馬県前橋から横浜に出てバラ学校に入学し、翌年同校の築地居留地移転(築地大学校になる)と共に上京した。築地に移るとすぐに新栄教会に通い始め、明治14(1881)年3月に石原保太郎牧師から洗礼を受けて新栄教会員となった。内田もやはり納所や小山と一緒に築地大学校および新栄教会で西洋音楽に目覚め、納所や小山と同様に音楽取調掛に進学した。卒業後は彼らと別れ群馬県師範学校に奉職し、唱歌の普及や作曲に努力した。内田が作曲した小学唱歌「秋景」(秋げしき)は大変人気があり当時良く歌われた。やがて、母校に戻り音楽取調掛の助教授、教授となり音楽教授法を講義した。その頃の教え子に三浦環や山田耕筰がいた。晩年は群馬に戻り県内の音楽教育に力を注いだ。
➄ 北村季晴(すえはる,1872~1931)
明治5(1872)年静岡に生まれ、明治10(1877)年に一家で銀座数寄屋橋に転居した。季晴少年は西洋音楽に興味を抱き築地居留地に出かけ、東京一致神学校(明治学院神学部の前身)などに顔を出しフルベッキ宣教師からオルガンを習うようになった。明治20(1887)年に東 京一致英和学校(築地大学校の後身)に入学し、朝夕の礼拝と新栄教会の日曜礼拝で讃美歌に出会った。この年、同校は築地から白金に移り明治学院普通学部になり、北村も白金に通うことになった。しかし、彼は初代総理であったヘボン博士から「君は音楽の才能の天分があるし、音楽を目指すなら明治学院よりも音楽学校の方が良い」と勧められ、東京音楽学校に転校した。同校卒業後は青森師範学校、その後長野師範学校に勤め、そこで明治33(1900)年に、現在も長野県出身者は誰でも歌えるほど県民に知れ渡っている「信濃の国」を作曲した。また、日本最初の創作オペラ「露営の夢」、和洋折衷歌劇「ドンブラコ」の作曲者として音楽界では良く知られた存在である。長野師範学校退職後は、東京音楽学校嘱託や三越呉服店の三越少年音楽隊を指導した。現在、長野県庁前に同氏の記念碑がある。
➅ 大塚淳(すなお,1885~1945)
父・大塚正心はクリスチャンの医師であり、ハンセン氏病院の慰廃園を開設し長く園長を務めた。母かねは山田耕筰の母ひさの妹である。 従って、淳は山田耕筰とは従兄弟関係にある。淳は幼い日両親に連れられて新栄教会に通った。大塚夫妻は息子の淳を明治学院に入れ、卒業後は医師の道に進むことを期待していたが、淳は音楽家を志望する。明治学院を卒業すると東京音楽学校に進学した。卒業後、慶応義塾のワグネル・ソサィエティーの常任指揮者、東京音楽学校助教授、教授、明治学院グレゴリーバンド、新交響楽団(現在のN響)および満州国新京交響楽団の常任指揮者を務める。慶応新応援歌の作曲や慶応義塾塾歌の編曲もしている。従兄弟で一歳違いの山田耕筰にとっては、淳は目標でありライバルでもあった。
➆ 山田耕筰(1886~1965)
明治19(1886)年6月に東京本郷で3人の姉、一人の兄と弟の二男として生まれた。一家はすぐに横須賀に引越し、耕筰は7歳まで住んでいたが家が焼け、長姉と一緒に二番目の姉夫妻が住む芝愛宕下に移る。そこで耕筰は近所のヤングマンが経営する第二啓蒙小学校に通う。しばらくして、父親も上京してヤングマン経営の聖書学館の事務を手伝うことになり、築地新栄町5丁目(現在の入船3丁目)にある第一啓蒙小学校内に一家で住み込む。ある日耕筰は小学校の大きな樫の木の看板が倒れてきて怪我をしたため、一家はヤングマンの住む築地居留地6番B棟に引っ越した。
自宅では両親や姉が毎日英語の讃美歌を歌い、主日には新栄教会に姉たちに連れられて通い讃美歌を聴き、知らず知らずにその旋律が身体に染み付いていった。また居留地の洋館から流れるピアノの調べ、墨田川の帆前船の船頭の親船を呼ぶ声など、築地居留地は耕筰の旋律の原点となった。10歳のとき父が療養のため一家は千葉に引っ越した。その後、長姉夫妻の元に引き取られ関西に移るが、波乱万丈の人生は自伝『若き日の狂詩曲』(中公文庫)を読んでください。
耕筰は明治33(1900)年6月のペンテコステに、後に岸田吟香の息子で麗子像で有名になった画家の岸田劉生と一緒に、数寄屋橋教会で田村直臣牧師から洗礼を受けた。やがて耕筰は従兄弟で一歳年長の大塚淳のアドヴァイスを受けて、彼を追って一年後に東京音楽学校を受験し合格した。その後の活躍は誰しも知るところである。
~最後に出席者全員で「赤とんぼ」を斉唱した~
3.おわりに 「本日の報告によって、この築地居留地が近代日本の西洋音楽の発展を担った青年たちを育んでいった、重要な場所であったことを知って戴けましたら幸いです。」と結ばれた。
定例報告会後、聖路加国際病院旧館前で記念撮影をした。引き続き、講演に関連した史跡(築地居留地6番B棟など)を中島先生のご案内で探索した。その後、同先生を囲んでのお茶会があり、多くの質問が寄せられ先生は懇切丁寧に答えられていた。
《定例報告会に参加して思ったこと、感じたこと》
中島先生は講演をされる時は、いつも研究に基づき学術的にご説明をされますが、今回はテーマが出席者にとって身近なもののため研究に裏打ちされた内容を平易にご説明され、且つ上記聖歌隊の皆さんも加わり、和やかな雰囲気になるように工夫されて、大盛況であったと感じました。
なお、明治学院の前身校(ヘボン塾、バラ学校、築地大学校、東京一致英和学校、東京一致神学校)及び明治学院で学んだ多くの先輩諸氏が近代音楽の発展に多大に貢献された貴重な事績を私達ゼミ生は知り、非常に誇りに思いました。そして、本学の今後のあるべき姿の一部が見えたように感じました。本学の卒業生や現役の学生は、おそらく同内容について知っておられる方は少数と思われます。
従って、今後も学内外で同講演の開催を望みたいと思います。 最後になりましたが、この機会を得、先生並びに築地居留地研究会の皆様などに感謝申し上げます。誠にありがとうございました。
(世話人:海瀬春雄)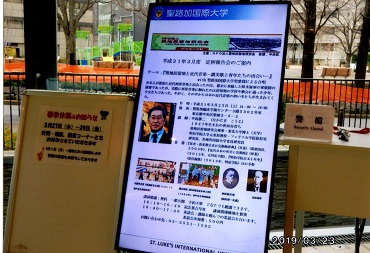
(写真:定例報告会のご案内)